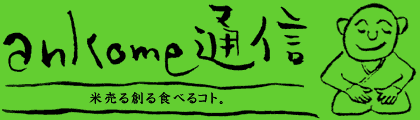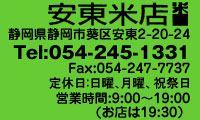| 旅する羽釜 ハワイ旅 5【最終回】 | |
 |
2017年5月20~25日、ハワイ州ホノルルにある日本米専門店「The rice factory honolulu」で、巨大胚芽米カミアカリの試食会のため羽釜スイハニング(炊き)してきました。これはそのレポートです。
その前にヒロのパシフィックツナミミュージアムへ。 「津波の発生域が近海ではないからPTWC(太平洋津波警報センター)からの警報で事前に避難できるんだよ。それにハワイは観光の島だからね・・・」 近海で津波が発生する日本ではハワイ島のようにはいかない。 午後からは、いよいよマウナ・ケアとキラウエアボルケーノへ。 麓へ降りると雨が降ってきた。交通量のある片側2車線の街道を通ってキラウエアボルケーノへ。 クレーターを巨大釜戸に見立てて羽釜を撮る! ところがなかなかいい場所が見つからない。それに天気が不安定でクレーターが見えたり隠れたり、思いどおりの絵がなかなか撮れない。あきらめて帰ろうとした時、駐車場の奥に一本のトレイルを見つけた。観光客もほとんど来ない閉鎖中のトレッキングコースの入り口だった。そこには誂えたかのように杭が一本立っていた。その上に羽釜を置くとこれがピッタリ!こうして撮ったのが上の画像。 flying hagama meets grand kamado! 宿舎戻ったのは7時過ぎ、すっかり遅くなってしまった。 こうして5日間のハワイスイハニング旅が終わった。 おしまい 画像上:旅する羽釜、超巨大釜戸に会う!キラウエアボルケーノ。 |
| 旅する羽釜 ハワイ旅 4 | |
 |
2017年5月20~25日、ハワイ州ホノルルにある日本米専門店「The rice factory honolulu」で、巨大胚芽米カミアカリの試食会のため羽釜スイハニング(炊き)してきました。これはそのレポートです。 ホノルルthe rice factory honoluluでのミッションが無事終了したあと2日休みをもらいハワイ島へ行った。 クルマで15分ほどの高台の一軒家がこれから数日過ごす家。 ところで、今回の旅の共はおなじみ田中隊員、高部隊員こと、田中夫妻。 備え付けのお米はカリフォルニア米だろうか?大粒だった。 ヒロは雨の多い町と聞いたとおり夕暮れ過ぎからまた雨が降り出した。 つづく 画像上:この一升羽釜は明治生まれの祖母の時代から我が家にあったもの。まさかこんな旅をするとは・・・。 |
| 旅する羽釜 ハワイ旅 3 | |
 |
2017年5月20~25日、ハワイ州ホノルルにある日本米専門店「The rice factory honolulu」で、巨大胚芽米カミアカリの試食会のため羽釜スイハニング(炊き)してきました。これはそのレポートです。
5月21日日曜日、今日のスイハニングはお昼からというので、少し寝坊した。 10時過ぎ、今日も日差しが強く蒸し暑い。牛島さんがクルマで迎えにやってきた。 今日はthe rice factory honoluluでスイハニング。 そのまま火加減しながら沸騰維持。ふと周囲を眺める。 そんな感傷に耽っている間に、羽釜からいい香りとあの音が聞こえきた。 how many minutes? how many minutes? how many minutes? how many minutes? カミアカリのおこげから、あのチョコレートを思わせる香ばしい香りがしている。 この後、地元の食関係のメディアの方も数名来られ、 旅する羽釜 ハワイ旅 番外編へつづく
|
| 旅する羽釜 ハワイ旅 2 | |
 |
2017年5月20~25日、ハワイ州ホノルルにある日本米専門店「The rice factory honolulu」で、巨大胚芽米カミアカリの試食会のため羽釜スイハニング(炊き)してきました。これはそのレポートです。
5月20日土曜日、今日は午前中カカアコ地区で毎週末行われるファーマーズマーケット、 7時半、牛島さんとスタッフ君、僕と田中ペアの5人で設営開始。 スイハニングはいつもアウェイ、毎度のことながら何が起こるかわからない。 ホッとするのもつかの間、珍しがってやって来たギャラリーが炊き上がったばかりの羽釜の周りに集まっている。 pan fry!(おこげを、こう表現していた記憶あり・・・記憶違いしているかもだけど) 午後はthe rice factory honoluluへ移動してもう1ラウンド。 この日は用意した1パウンド(約450グラム)入りお試しパックのカミアカリはみるみるうちに売り切れた。 画像上:ザ、カミアカリ! |
| 旅する羽釜 ハワイの旅 1 | |
 |
2017年5月20~25日、ハワイ州ホノルルにある日本米専門店「The rice factory honolulu」で巨大胚芽米カミアカリの試食会のため、羽釜スイハニング(炊き)してきました。これはそのレポートです。
海外で日本の米を専門に販売しているWakka Japanの出口さんが玄米食専用品種カミアカリを販売することになり、 当日のオペレーションや機材などの細かな点はメールのやりとりでほぼ決まった。 5月20日の21時過ぎの便でホノルルへ、5月19日午前中に到着。 準備が終わった後は近所のスーパーで食糧調達。 ※ESI(エクストリーム・スイハニング・インターナショナル)カミアカリの勉強会「カミアカリドリーム勉強会」の炊飯担当部隊。会のスピンアウト企画としてはじまり、独自の炊飯活動を実践中。 画像上:ファーマーズマーケットにて |
| 200人スイハニング | |
 |
去る4月14日、200人の大学生相手にスイハニングワークショップを行った。 羽釜は全部で20釜、今まで見たことのない数。。。 炊き上がったご飯は、アツアツのうちに、おむすびを作ってもらった。 米どころ出身の学生さんからも「めっちゃ美味しいです!」と言葉が出るほど会心の出来映え。 <感謝をコメて> |
| スイハニングのルーツを探る旅 6 | |
 |
場末の米屋がいつしかライフワークになったスイハニング(炊飯)のルーツへの探求。
この形の土器は、弥生時代から古墳時代初期に使われていたもので、 この台付甕型土器、不思議なことに蓋に相当する遺物が出ていない。 もしこれが事実なら、台付甕型土器による調理は、「煮る、焼く、蒸す」の複合加熱、つまり炊飯ではないことになる。 一般的には、考古の専門家の解説では「煮炊き=炊く」と表現する場合が多く、それ自体は誤りではないが、 その後古墳時代となると、朝鮮半島から最新設備が入ってくる。 つづく 画像上:春の海、三浦半島胴網海岸でスイハニング(2016)周辺を15分ほど柴刈すれば二釜分以上の燃料はすぐ調達できる。この列島のなんと豊かなことか! |
| スイハニングのルーツを探る旅 5 | |
 |
場末の米屋がいつしかライフワークになったスイハニング(炊飯)のルーツへの探求。
「人口は、縄文ピークで26万人、それが後期で10万人という試算がでています。寒冷化のほかに、大陸からの病気説もあるそうです。弥生は60万人、ピークは100万人と大増加、やはり水田稲作がヒットしたことは間違いないですよね!」 いづれにせよネイティブニッポン列島人(縄文人)ライフを継続する人は減り、 しかしそのニッポン人がいきなり「炊飯」を完成させたわけではない。 つづく 画像上:有機米生産者、松下さんの作業場で度々行われる講座で彼の米をスイハニング(2013)土鍋は1700℃のガスの炎に出会ってはじめてその秘めた力が覚醒されたと思う。 |
| スイハニングのルーツを探る旅 4 | |
 |
場末の米屋がいつしかライフワークになったスイハニング(炊飯)のルーツへの探求。
前回書いたように、木の実に比べれば そもそも渡来人が運んできた稲の種類はごく限られた種類だったらしい。 ただひとつ考えどころなのが出会ったばかりのご先祖さんたちにとっての米は、 ここは多くの人で空想してほしいポイントなんだけど、私はこんな空想をしている。 つづく 画像上:フレンチレストランでカミアカリスイハニング(2013)1700℃の炎の火加減をしながら、木が燃える800℃の炎と金属羽釜の意味に気づく。 |
| スイハニングのルーツを探る旅 3 | |
 |
場末の米屋がいつしかライフワークになったスイハニング(炊飯)のルーツへの探求。
「木の実に比べたら、どうってことね~な~」 アクもなく少ない燃料であっという間に消化吸収できるデンプンに調理できる、 本格的に稲作が始まるのは精緻な土木技術によって生まれた洗練された水田稲作が始まった頃のこと、 つづく 画像上:松坂屋静岡店の初売りイベントで5釜連続で玄米食専用品種カミアカリをスイハニング(2017) |