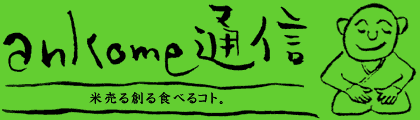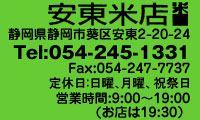| スイハニングのルーツを探る旅 2 | |
 |
場末の米屋がいつしかライフワークになったスイハニング(炊飯)のルーツへの探求。
「植物種子を加熱調理するための成熟した技術を持ったご先祖さんたちの前に『米』がやって来た!」 ニッポン列島がまだ大陸と地続きだった時代、大型動物を追いかけて移動してきた先人たちは、 つづく 画像上:初の海外スイハニングはフランス、フェール城「能」イベント(2013)ピレネーの軟水とゲランドの塩でカミアカリお結びを作る。 |
| スイハニングのルーツを探る旅 1 | |
 |
炊飯はニッポン列島で生まれた独自調理技術だということは、ここでも何度か書いてきた。 その技術はどういう経緯で生まれたのかを知りたくて 縄文時代の晩期、渡来人によって稲が大陸からやってきて以来、 つづく 画像上:南阿蘇で地元の有機米をスイハニング(2014)地元の米を地元の水と燃料でスイハニングする醍醐味は格別! |
| アートロ「登呂でオレらは、考えた。展」 | |
 |
2012年実験準備段階から関わり今年で5年目、 アートロでの私の研究テーマは水稲と炊飯技術の歴史とその変遷。 考古学や経済学、社会学といったカテゴライズされた理解の仕方とは少し違う、 「登呂でオレらは、考えた。展」 アートロホームページ 展覧会開催告知動画 |
| 今年もヤツらがやってくる! | |
 |
毎年恒例、節分の日、アンコメに鬼がやって来ますよ~。 2月3日(金)16時15分頃 |
| アンコメ感謝祭 1月21日土曜日! | |
 |
1月21日土曜日(10~14時)アンコメが日頃の感謝をコメて一日だけのイベントやります! 出店者さま商品リスト <北海道豊頃町:互産互消プロジェクトチーム> ・海鮮モノ(毛ガニ/シシャモ/鮭トバ) <マル鉄商会> 【商品】 <創作珈琲工房くれあーる> ・スペシャリティコーヒー豆各種 <富士宮やさし菜農園> ・白菜 <蒲原カネジョウ> ・いわし削り節 <イベント詳細> |
| 初スイハニング! | |
 |
2017年の初仕事はスイハニング(炊飯ing)から。 じつは今年は松坂屋静岡店の開店85周年、 1月2日9:30開店とともに連続で5釜、7升スイハニングします。 松坂屋静岡店の開店85周年記念福袋「新しい卵かけごはん」 Ⅰ,元旦に生んだ“美黄卵”使用! Ⅱ,幻のお米 カミアカリ使用! Ⅲ,トッピングには、醤油ではなくあえて「塩」を使用! ※85袋の中に1袋つだけアンコメ店主による「出張スイハニング券」も入ってますよ。 販売場所は、1/2(月祝) 北館1階けやき通り入り口です。 |
| 探粋華物 | |
 |
2016年も無事12月31日を迎えることができました。 来年2017年は、 来年もどうぞよろしくお願い致します。 新年は1月6日より営業致します。 |
| 餅切り抜刀斎、見参! | |
 |
今年もあっという間にお餅の日。 12月の初旬には精米をしておいた原料米を餅工房へ運び職人に搗いてもらう。 餅切り抜刀斎。 今年もあと数日、 ※お餅の販売は30日まで!お早めに!ご注文はコチラへ↓ |
| 新米入荷最終盤。 | |
 |
毎年のことながら超多忙な秋。 デスクのある部屋の窓から見える裏庭のヤマボウシ、 日照不足の影響で各地減収とはいえ、品質食味ともその心配をよそになかなか良い。 |
| カミアカリ@D&D | |
 |
D&Department静岡で9月から始まっている期間限定企画「静岡のおいしいお米」 巨大胚芽米カミアカリ 通常の3倍余りある大きな胚芽を持つ米で、 物語り満載のこのお米を、9月29日から10月12日まで shopでは1kg、キューブ型300gの販売もしています。併せてご利用ください。 |