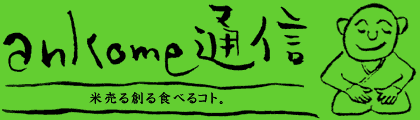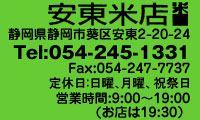| 水田徘徊2017 長野県伊那谷ザライスファーム再訪。 | |
 |
長野県伊那谷で今年新規就農にして初作付のカミアカリ、初物づくしの彼らザライスファームイナの大胆な挑戦が気になって収穫のその日、再び訪ねてみた。午前中、佐久の黒田さんの田んぼ訪ねてから伊那へ入ったため、カミアカリはすでに収穫されてはいたが、はざ掛けされたばかりの彼らのカミアカリをじっくり拝むことができた。 実験栽培ということもあり、生産コストは度外視、できることは全部やりました的な気合いの入った栽培。良い意味で贅沢な作りは、彼らがFBページでもアップしていた生長過程の画像が象徴するとおり、見事な姿で育ってくれた。標高が高く、谷あいで日照が充分ではなく、用水とはいえ最上部の冷水がそのまま流入する環境は、お世辞にも良い場所とは言い難い。しかも今年の天気ときたら・・・早生品種であるカミアカリは満足な登熟(成熟)をしてくれないのではないかとちょっぴり脳裏をよぎった。これが化成肥料ならなんとかなるだろうとも思うが、地力だけに頼った無施肥となれば、もはや博打以下というしかない。それでもこの挑戦を僕は面白いと思い作付を了承してしたのだった。 カミアカリを発見育成した松下さんをはじめとして生粋の酔狂者がカミアカリ好きとばかりと思っていたが、はざ掛けされた彼らのカミアカリを眺めながら、もしかすると、カミアカリが酔狂者を好むのかもしれないと感じるほど、手のひらの中にあるカミアカリは見事な出来映えだった。これを見ながら過去にカミアカリについて書いた記事のことを思い出していた。記憶の地平【16】のことである。 あとはたべてみる。だけですね。 |
| 水田徘徊2017 佐久市黒田さん | |
 |
黒田くんと知り合いになって何年だろう?長野県の佐久で新規就農して間もない頃、松下さんの著書「ロジカルな田んぼ」を読んだと言って電話してきたのがきっかけだった。その週末には松下さんの田んぼの畦傍にやって来て、稲の生命生理について延々と対話していた。その行動力もさることながら、そうせざるを得ないほどに飢えていたのだろうことも想像できた。手帖で確認したら2013年9月15日のことだった。僕はその翌年から一年に1回、佐久にある黒田くんの田んぼへ通うようになった。 9月24日、収穫時期の真っただ中、今年も黒田くんの田んぼを訪ねた。土地もなければ道具もない。ないない尽くしから5年、今は条件の良い田んぼを借り、中古ながらもコンバインも持った。なにより結婚をし子どもももうけた。すっかり地域に根付き、未来を期待される人材に成りつつある。そんな彼は今日が29年産米収穫初日であった。 全体で約4町歩ほどになった田んぼの多くは江戸時代初期に築かれた五郎兵衛新田にある。おもな栽培品種はコシヒカリ。今年の気まぐれな天気は有機肥料をベースに栽培する生産者にとっては、なかなかコントロールの難しい年だろうと想像はしていたが、黒田くんも例外ではなかったようだ。効くべき時に効かず、効かなくてもいい時に効いてしまう。有機物の分解を微生物に任せるが故の難しさがそこにある。それでも米は実り収穫の時を迎える。美味しいかそうでないかは、所詮人間の欲の話しだと稲たちは嘲笑ってるのではなかろうか? 黒田くんは、これから10日間かけて収穫作業を進めていく。「アンコメさんには、あの田んぼのを送りますから!」営業トークもすっかり板についてきた。29年産佐久黒田米、楽しみである。 画像上:佐久市「五郎兵衛新田」遠く見える頂きは浅間山 |
| 水田徘徊2017 福島会津喜多方の菅井さん | |
 |
奥久慈大子町の大久保さんの続き。(今回は長いです) 大子町の夜(8月26日)は、お酒の量に比例して与太話も増えつつ更けていった。翌朝、大久保さんのところで自慢の飯をたらふくいただいてから次の水田徘徊へ旅だった。松下さんとはここで別れ、長野県の佐久からやって来た黒田くんの軽トラに乗り換えた。目指すは福島県の会津で有機米を栽培している菅井さん、田んぼは会津地方の最北地、喜多方市熱塩加納町。下道&軽トラ、ヒッチハイクのような旅に興奮しつつ出発した。道中は休憩を含め5時間ほど、奥久慈から会津までの道程は当然のことながら田んぼ!田んぼ!田んぼ!そんな景色を眺めつつ、狭いキャビンの中で話しに華が咲く、そのほとんどは僕が最近気になっていることを、年齢差20年、30代の黒田くんがどう思うかについて質問することからはじまった。 興味を持った人なら技のあるなしに関わらず稲を育てることができて、質や量も細かいこと言わなければ米にはなるよね。農薬や肥料がなくてもで地力と水と太陽さえ照ってくれさえすれば米は生まれるでしょ。そういう米と松下さん、大久保さん、菅井さんが生業として栽培してできた玄人の米が、今、同じ地平で語られたり、評価されたりしてることに、僕は何というか居心地がよくない感じがするんだ・・・とはいえ、考えてみれば、この20年僕が追求してきた価値の発見と創造には、このような素人的というかプリミティブな発想によって紡いできた気もしているんだ。つまりカミアカリの栽培理念には、このエッセンスを忍ばせていることは僕がいちばん知ってること。紛れもない事実なんだよ。これをどう考えたらいいだろうか?ただたんに年を取って頑固になっただけのことなんだろうか・・・?
黒田くんと会話する菅井さんはいつになく先輩口調、それを少し離れたところで聴きながら写真撮影に精を出す。ここの除草体系は紙マルチ、4月でもどうかすると雪が降るこの土地では、藤枝の松下さんのように何度も代掻きをして草の個体数を減らす作業はできない。そこで菅井さんはロール状の紙を敷きながら田植えする方法(マルチ)によって初期雑草の抑草をはかり有機栽培を実現している。草対策はこれで良いとしても、温暖な会津盆地とはいえ、熱塩加納町は北の奥座敷、盆地を陸上競技場に例えるなら、アリーナではなくスタンド席の最上段。つまり気温が低く日照時間も限られるところ。たびたび冷害に悩まされるところなのだ。戦後入植した初代のお爺さんによれば、この地に20軒入植するも残ったのは菅井さんを含めわずか2軒だったというから、当時としては相当に過酷な土地だった。それ故にお爺さんたちは農閑期は出稼ぎに出たという話を晩年にお聞きしたことがあった。つまりこの土地は、昨夜味一での話題となった「よい場所」では、けっしてなかったということだ。しかし菅井家は代を重ねながら、その土地を「よい場所」に変えてきた。正確には良し悪しに関わらず、すべてを引き受けその土地でしかできない稲作を発見創造してきたのではないかと思っている。カミアカリに現れる、あのほかでは味わえない木の実を思わせるような深い風味を味わう時にそれを思うのだ。 日が沈み、ビール片手に菅井さんがぽつりと言った。「長坂さん『自然栽培』ってどう思いますか?」それを聞きなんとタイムリーなことかと内心思った。昼間、軽トラで黒田くんと話したことの中に、この四文字が少なからず関係していたからだ。「気分や姿勢としては理解できる。けれど、そもそも日本語として誤りがあるよね。だって自然と栽培は相反する出来事だもんね・・・」と答えてから、菅井さんの言いたいことは、たぶん僕がここのところ感じていることと、ほぼ同じことだと承知した。つまりこの過酷な土地で代を重ねながら稲の生命生理を尊重しつつ、人が生き抜く術を研いてきた者たちが生み出した米と、ある日やって来た彼らが言うところの自然栽培なる過程で生まれた米が、同じ地平で語られることの居心地の悪さのことだ。 かなり大雑把だがこの国の稲作の歴史とはこんなものだったと承知している。田んぼは土木工事によって稲専用に栽培を目的として人工的に作られたもの。古代においては容易に平らを作るために小さな田んぼだった。肥料というアイデアもない頃は休耕することで地力が回復することに気付いた。太閤検地によって圃場に課税されるようになってから毎年同じ田んぼで一粒でも多く実るよう栽培するために、他からエネルギーを補充する技術、つまり肥料というアイデアが本格化したらしい。国力が石高の時代は新田開発のために、列島の隅々まで山を穿ち川の流れを変えた。第一次世界大戦の頃、爆弾を作る過程で窒素固定の技術が進み化学肥料が生まれる。これによって収量は飛躍的に増え、同時に人類は爆発的な人口増加を果たした。それらを同時に支えたのも近代科学が生んだ農薬だった。近代科学が生んだ打ち出の小づちみたいな農の背後で、様々な問題がこの国に露呈し始めたのは高度成長期、そのアンチテーゼとして、農薬、化学肥料以前にあった農への回帰だった。後にそれは有機農業と呼ばれ今に続いている。菅井家はその時代に先進的に有機稲作へ回帰した人たちのひとりだった。 農家でなくても農ができる時代。いわば農が民主化されたような今、様々な場所で様々な過程によって米が生まれている。そのどれもが米であって、たべものとして同じ地平にある。玄人か素人の別はない。けれど本物か本物でないかの洗礼は受けざるを得ない。今回の旅はこのことについて考えるよい機会だった。まだ答えらしい答えは導き出せないでいる。11月に行うカミアカリドリーム勉強会ではこれをテーマにしようと考えている。立場や世代を超えていろんな意見を聞いてみたいと思っている。 画像上:29年産菅井カミアカリは身体を作る期間中の日照不足から茎数が少ない、それと若干いもち病の心配も出てきている。収量は計画よりは減ってしまいそうだ。ここから45日間の天気が米質を決める。ただ祈るのみ。 |
| 水田徘徊2017 奥久慈大子町の大久保さん | |
 |
夏の終わりに茨城と福島へ旅に出た。思えば学生時代、先輩から譲ってもらったオートバイで北を目指して旅をしたのもちょうどこの時期だった。この時が初めての東北の旅、国道4号線を北上するにつれ、肌で感じる涼しさに南北に伸びる列島を感じたものだった。今回は松下の愛車に揺られ高速道路を北上する。ワンボックスのキャブオーバー、若い時と違いもう少ししなやかな足回りが恋しくなる。そんな頃、茨城県の最北部、久慈郡大子町に到着した。 「昨日まで曇天、今日は久々の太陽ですよ・・・」久々に会う大久保さんとの会話も、やはりお天気のこと。ご多分にもれず大子町も曇天続きだったそうだ。しかし日照不足を心配しつつも目の前にある早生品種(カミアカリ、コシヒカリ)たちは、そんな心配をよそに見事に穂を垂れている。日照は少なかったものの気温は平年並み、ゆえに積算温度はほぼ例年どおり積み上がったことが功を奏したらしい。「まあ、数日遅れくらいですかね・・・今年はカメ(カメ虫)いないし、まあそこそこいけるんじゃないですかね~」。品質にも自信が持てている様子だった。 高温や冷夏、日照不足に空梅雨、台風に大雨・・・毎年毎年に列島中でいろいろなことが起きているが、僕の知る限りこの大子町は大きな影響を受けることがあまりなかったように思う。「人が古くから住みついているところはそれなりの理由があるんだって考古の先生が言ってぜ・・・」と、いつも行く味一(大子町ダウンタウンにある焼肉&おむすびの人気店)で一杯やりながら松下が言った。「田んぼだってそうだろ、放棄された田んぼには理由があるんだ、いい田んぼはみんな知ってんだよ・・・」。就農して5年、最近になってようやくいい田んぼが借りられるようになった黒田くんにとっては、それは目の前の現実そのものだと松下さんも大久保さんも承知の上で話をしている。大切なのは、こうして旅をして別の土地に来て自分の足元を俯瞰すること。栽培技術を学ぶことと同じか、それ以上にこの皮膚感覚は大切なことと思う。これが分かってはじめて、自分の足元でしかできない米を考えることができる。と僕はいつも感じている。農業者でもないのに生意気なのではあるが。 画像上:反収7.5俵というあたりの大久保コシヒカリ、止葉(とめは)の色が抜け始めれば登熟も後半。今年もいい出来映えだ。 |
| 水田徘徊2017 森、磐田再訪 | |
 |
毎年、世の中がお盆休みのこの時期、静岡では早生品種コシヒカリが収穫時期となる。かつてはお盆が明けてからが恒例だったものだが、昨年28年産は10日から収穫が始まった。30℃を軽く超えるような気温の日が連続したためだ。アンコメにとっては毎年ここから新米キックオフ、出来が気になってしかたない。そこで毎年、お盆休み中の1日はドライブがてら森と磐田を訪ねることにしている。仕事気分が抜けた気ままドライブのため生産者さんにはアポなし。田んぼに行って会えればラッキーという具合でフラッと訪ねるのだ。 森の堀内さんを訪ねると、田んぼにはまだ稲があった。まだ収穫していなかった。堀内さんが米の工場(調整乾燥、籾擦り、袋詰めをする施設)から出て来た。「この天気じゃ稲刈りできんな~これじゃまるで梅雨だもんな~こまったもんだや~」その言葉どおり、ここのところ真夏のギラギラ太陽を見たことがない。考えてみれば梅雨明け以降、夏らしい青空はほとんどなく梅雨のようなお天気が続いていた。おかげで例年よりもややゆっくりとした生長を具合だという。それでも稲は今すぐに収穫しても差し支えない色に仕上がっている。「晴れてくれればすぐにでも刈るんだけんど・・・」と堀内さん。どうやら明日、明後日も雨の予報。気温が低いのは人間にとっては楽だが、稲にとってはこの日照不足、我慢の時なのだろう。 堀内さんのところを後にし磐田の太田農場さんへ向った。太田さんは休業中だったため田んぼだけ見てきた。周辺とは明らかに違う色あい。そもそも薄めに移植しているから株間に余裕があることも「スカッと」見える原因でもあるが、実に良い色の抜け方をしていた。こちらも森町同様に、いつ刈っても良い状態だった。お盆休み明けの天気はどうなることやら?「カラッと晴れる夏の青空よ早く来~い!」 画像上:こうべを垂れる森町堀内米コシヒカリ
|
| 水田徘徊2017 長野県伊那谷ザライスファーム | |
 |
伊那谷の東、南アルプスの仙丈岳の麓、伊那市長谷村南非持地区で今年から稲作を始めた農業法人「the rice farm nagano ina」へ行った。ザ ライス ファーム ナガノイナ?と聞いて勘のいい方は気付いた方もあろうと思うが、5月後半にカミアカリスイハニングのために出向いたハワイの米屋「the rice factory honolulu」と同じグループ会社で、稲作を担うチームがこの農業法人だ。社長の出口氏が肝入りで始めた新事業で出口氏本人と彼の学生時代の友人の二人で現場を取り仕切っている。じつは今年2017年(29年産)から巨大胚芽米カミアカリを実験レベルながら栽培を開始したこともあり、カミアカリの育成者である松下さんと視察に出向いたというわけだ。文字にすると、やけに堅苦しく見えるが、稲作を始めたばかりの後輩たちがカミアカリ栽培というビックチャレンジに、オッサン2人が心配で世話を焼きに行った・・・という風だとご理解いただきたい。(苦笑) 彼らが通称「天神の田んぼ」と呼ぶ棚田にカミアカリがあった。天神の田んぼと呼ぶには理由がある。じつは田んぼのある棚田の上段に小さな祠があり、近所の方の信仰の場として古くから「天神さん」と呼び、親しまれてきた歴史ある場所だった。そんな地域のカミサマの懐に、カミアカリが育つことになったことに縁を感じつつ、まずは彼らと彼らのカミアカリの無事をお祈りさせていただいた。 ここで栽培されるお米は、同じグループ会社が海外で経営する米屋で販売することになっている。じつはそれが無農薬無肥料で栽培されている大きな理由である。国によって使用できる農薬や肥料の基準が異なるために、同じお米であっても販売が容易にできる国と、そうでない国があり、各店舗で共有しずらい点を払拭するために「いっそ農薬や肥料(化学、有機)などを何も使わないことで、どの国でも販売できるようにする!」という大胆な発想のもとに計画されたのだった。 長年耕作放棄地だったこともあり、地力は充分に回復している。その証拠にカミアカリの葉色(ようしょく)は青々としていた。青々とした葉色は、その田んぼに窒素分など稲の生命生理に必要な成分が充分にあることを示唆している。それも化学合成によって精製された「それ」ではなく、長年に渡りここで繁殖してきた植物や動物が分解と再生によって蓄積されてきた「それ」である。こうやって自然に蓄積されたエネルギーや微量要素を「地力」という。お米などの収穫物にして人が収奪しなければ土地は肥沃になっていく。出口さんらは、その営みの中での稲作を考えているのだ。 実験栽培とはいえ、この田んぼのカミアカリは思いのほか立派に育っている。一株で尺植だから株間は充分、スッカスカだから除草もまめにできていることから他の草に栄養を収奪されることはほぼない。ただし問題はこれからだ。受粉から収穫までの期間のことを登熟期というが、標高800mで谷あいのこの土地で、充分な日照と温度が今後一ヶ月間で充分に確保できるだろうか?満足な登熟をしてくれるだろうか?高温障害の心配をしなくていい分、そのことが気がかりではある。こうゆう栽培であれば窒素過多による稲の倒伏はないが、目標収量が下回れば「人」が倒伏してしまう。農とは土地の持つ地力、その年の日照や気温、その上で選ばれた稲品種、それらの組み合わせの妙が、人が生き抜くための知恵として研鑽されてきた。考えてみれば、彼らのそれは今始まったばかりなのである。 画像上:標高800m、眺めの良い田んぼで育つカミアカリ。 |
| 水田徘徊2017 北海道蘭越町宮武さん | |
 |
北海道のお米は永く扱っていながら、これまで「人」にフォーカスしてこなかった。それが2016年、カミアカリの勉強会メンバーである横浜の同業者、加藤さんから蘭越町の宮武さんを紹介された。彼から預かった米を試食した時に、「北海道にも、こういうお米があるんだ・・・」と改めて再認識したことから、その年から宮武さんの米を扱うようになった。ここでいう「こういう米」とは「工芸的な米」のことをいう。もっとはっきり言えば「工業的でない米」のことだ。 北海道や東北地方北部の熱心な稲作家は、たいがいの場合、大規模化の道を辿る。一枚の田んぼが一町歩(10反:3000坪)なんてのは最低単位。それだけの規模となれば、田んぼを平らにするにも、それなりの設備を必要となるくらい、機械による管理が前提の稲作になる。それはけっして悪いわけではないが、そうやって生まれたお米に、たべものとしての「色気」があるかと問われると、少し立ち止まって考える時間が欲しくなる。そもそも、米に色気が必要であると考えるのは、たぶんマイノリティーだと承知しているので、この話はあくまでも「アンコメ好み」の範疇のこととして聞いてほしい。 藤枝の有機米生産者の松下さんもよく言っているのだが、人と稲の距離感ってものがあって、目がいき届く、気持が通ずるちょうどサイズというものがあるらしい。そのちょうどいいサイズが松下にとっては田んぼ一枚が3反、大きくても4反くらいだという。一枚が一町歩以上あれば作業性は格段に上がるが、稲との距離が遠くなるのだという。まったくもって論理的ではないが、モノづくりの経験が少しある僕のとって、それはとてもよくわかるのだ。職人技が発揮できるサイズ。つまりそれが工芸的という言葉の意味だとわかってほしい。それに相当するような北海道育ちをずっと待ち望んでいたところに昨年、宮武さんを紹介されてのだ。 千歳空港からクルマで約2時間、蘭越町の宮武さんを訪ねた。飛行機から見えていた厚い雲のとおり下界は曇天、気温21度、短パンとTシャツではあきらかに寒い。聞けば昨日は30度以上あったという。そんな天気ゆえに、楽しみにしていた羊蹄山も裾野がちょっぴり見えるくらいの残念なお天気ながら、稲トークはとても盛り上がった。それは今回の旅に藤枝の有機米生産家、松下さんと、宮武さんを紹介してくれた加藤さん、それに最近長野県の伊那で稲作を始めた出口くんが加わったからだ。 北海道の品種といえば「ななつぼし」「ゆめぴりか」の2品種。宮武さんもこの2品種は当然栽培しているが、今回どうしても見たかった稲が2種あった。「Y」と「S」だ。訳あってあえてイニシャルとしたが、アンコメが色気を感じているのがこの2種。(「Y」はすでに店頭のみ販売中)それが、どんな環境でどんな設計で育っているのがどうしても見たかった。そもそも、それらの栽培に取り組む宮武さんという「人」を知りたかった。 中山間地に大規模な土木工事で築かれた田んぼ。棚田というには巨大すぎる法面はさしずめで古代の墳墓のよう。1枚が約5反分が4枚。そこにお目当ての稲があった。「どうです?」と宮武さんから問われたので「品がいいね」と答えると、ニヤっと顔がほころばせながら「そうでしょ!Yは上品なんですよ!」とうれしそうに言った。以前、彼が電話でこんな風なことを話したことを思い出した。「『ななつぼし』や『ゆめぴりか』は、ぼくに言わせたらデジタルなんですよ。そこへいくとYやSはアナログ、関われる余白がたっぷりあるんです。手を掛ければ手を掛けたなりの答えが返ってくるんですよ。だから面白い・・・」。 北海道の品種はどれも耐冷性に優れる。山から直接入るような水温の低い水の水口でも立派に育つ姿を見て松下が驚く。その性質を引き継ぐ品種と良食味米の系譜のルーツと呼ばれるような品種の血を引き継いだ「Y」と「S」。その生い立ちを畦傍で眺めながら聞き、ようやくそれらが持つ「色気」の意味の一端を理解した気がした。29年産は順調に行けば10月中旬には入荷するだろう。秋の楽しみがまたひとつ増えた。
画像上:宮武さんと彼の自慢のYとSが育つ田んぼ。北海道の標準的な田んぼサイズに比べればはるかに小さい。しかし、それが彼らしい稲作、稲と対話をしながら育つ、ちょうどいいサイズだと現場を見て納得した。 |
| 水田徘徊2017 磐田太田農場 | |
 |
前回、森町堀内米のつづき。 森町から太田川沿いに南へ移動すること30分、福田と書いてフクデと読む、水田稲作家にとっては縁起いいの町の川上に太田農場さんはある。静岡県内では早い時期に田んぼの基盤整備の進んだ一等地、一枚の田んぼが5反分以上もあるような大きく作業性の良い田んぼで仕事をしている。こんな恵まれた環境でありながら、それに奢れることなく、収量を求めず、むしろセーブして高品質を求める稲作を実践している若手生産家です。 太田さんのお米の品質は見た目からして立派。とくに玄米品質はピカイチ!玄米で購入されるお客様の多いアンコメにとって、この品質はたいへん心強いです。28年産では、コシヒカリとハツシモの2品種を販売。とくにハツシモは本家の岐阜産に劣らない、むしろ「太田さんのハツシモ」と言えるくらいの個性を持った米が表現されていることから、ファンも多いお米です。 29年産については、今のところ生長は順調そのもの。じつはここ2年、太田さん自身はあまり満足のいく仕上がりではなかったとのこと。そこで29年産ではその部分を修正するべく肥料体系を見直したとのこと。「3年連続は許されませんからね~」と自分に厳しいところは、本当に頼もしいです。 太田川を用水とするこの地域では若干の水不足が懸念されていましたが、ここのところのまとまった雨のおかげで、その懸念も払しょくされたようです。早生品種のコシヒカリはちょうど今頃(7/13)出穂が始まった頃、収穫は森町の堀内さん同様、8月お盆休み頃からとのこと。静岡が一年でいちばん暑い時期の登熟(米が熟す期間)は、徹底した水管理で乗り切ることと思います。稲作の基本の「き」のできている太田さん、そんな心配は御無用というところでしょうか。 つづく(次回:北海道蘭越町宮武さん) 画像上:7月4日、コシヒカリの幼穂(ようすい)。小さいながらすでに穂のかたちになっている。 |
| 水田徘徊2017 森町堀内米 | |
 |
毎年6月の終わり頃から田んぼへ出かける。 先週(7/4)、静岡県の西部、森町と磐田へ行ってきた。 まずは森町堀内米。 アンコメではここ数年、堀内米は3品種(コシヒカリ、きぬむすめ、にこまる)を販売している。 つづく(次回磐田太田農場さん) 画像上:にこまる、株間の広くとって植えている(疎植)がよくわかります。 |
| 薪 (も)あります。 | |
 |
スイハニング(炊飯)には欠かすことのできない薪。 出所のわかる地元の木、わずかとはいえ地元の山を守ることにも貢献できることがうれしいです。 地元の木を地元の人が使う。 株式会社ソマウッド |